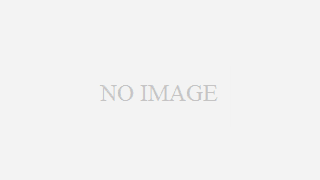 uncategorized
uncategorized 「圧密」について、分かりやすく解説!
圧密は、特に粘土質の地盤で見られる現象で、建物や道路、ダムなどの土木構造物を建設する際に重要な課題です。地盤に大きな荷重がかかると、地中の水がゆっくりと押し出され、長い時間をかけて地盤が沈下します。圧密は時間が経過してから影響が現れるため、...
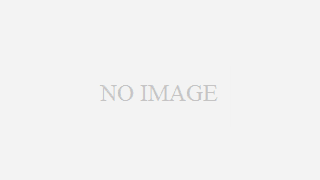 uncategorized
uncategorized 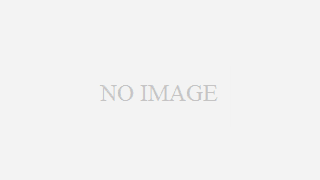 uncategorized
uncategorized 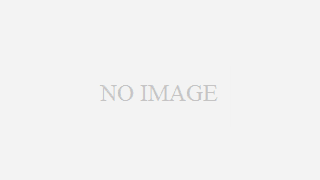 uncategorized
uncategorized 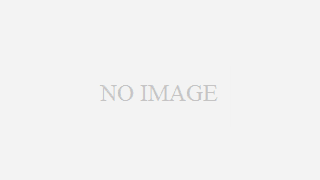 uncategorized
uncategorized 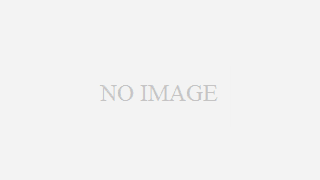 uncategorized
uncategorized 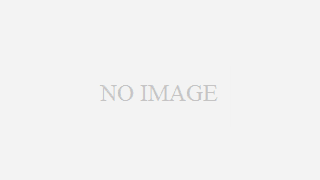 uncategorized
uncategorized 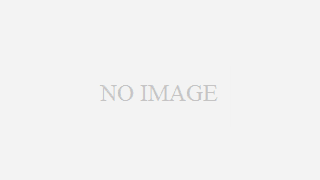 uncategorized
uncategorized