ダムやトンネル、地下鉄工事などで「水の浸入を防ぐ技術」が必要不可欠です。その中でもよく使われるのが「遮水壁(しゃすいへき)」です。遮水壁とは、地下水や雨水が地中を通って漏れ出すのを防ぐための壁状の構造物のことです。ここでは、遮水壁の仕組み、種類、工法などを分かりやすく解説します。
1. 遮水壁の役割と必要性
遮水壁は「地盤の中に造られる人工的な壁」で、地下水や汚染水の移動を防いで、周囲の構造物や環境を守ることを目的としています。
たとえばダムでは、遮水壁を設けることで、本体の下や周辺から水が染み出すのを防ぎ、堤体の浸食や空洞化による安全性の低下を防ぎます。また、地下鉄などの地下構造物では、地下水の浸入が工事や列車の運行等に支障をきたすため、遮水が重要となります。
地下水や汚染水が地盤に広がるのは、地盤が小さなすき間を有した構造であり、その間を水が自由に移動できるためです(この現象を「浸透流」と呼びます)。遮水壁は、このような水の移動経路を遮断し、浸透や汚染拡散を防ぐ役割を果たしています。
2. 遮水壁の代表的な種類
遮水壁の種類
- 連続地中壁
コンクリートやセメント系の材料で連続した深さの壁をつくる方法です。高い遮水性と構造的耐力を持ち、地下構造物の外壁や大型ダムの遮水に使われます。深い場所まで連続で不透水層を作れるため浸透を効果的に遮断できます。 - トレンチカット工法
地面を長い溝(トレンチ)状に掘り、その中に不透水材料(セメント、ベントナイトなど)を注入して壁を形成する工法です。施工が比較的単純で、経済性が高いのが特徴です。 - 鋼矢板(シートパイル)遮水壁
鋼製の矢板を地中に打ち込んで連続した壁を作る手法です。施工速度が速く、撤去も可能なため仮設用途に向くことから、仮設の堤防や港湾、防波堤工事でよく使われます。鋼材の腐食や継手からの漏水に注意が必要なので、防食塗装や止水材の設置などの検討が必用です。 - ジェットグラウト
高圧の水やセメントスラリーを噴射して既存地盤を攪拌・固化し、柱状の遮水体を作る技術です。狭隘地や深さが必要な箇所で有効で、狙った位置に局所的に高強度の不透水体を形成できます。
留意点(デメリット)
- 材料費:遮水壁の工事は、セメントなどの固化材や資材を現場まで運ぶ費用がかかります。材料費や運搬費でコストが高く感じる場合がありますが、遮水壁を作ることによって工期短縮や、作業ヤードの確保による作業の手間や人件費を削減できます。最終的に「早く終われて人の数も減らせる」ので、全体の費用で見るとバランスが取れるケースが多いです。
- 浮力の影響:遮水壁の中に流し込む材料は、液状材なので物を浮かせる力(浮力)があります。地下に埋めたパイプやマンホールが、浮き上がってずれたり壊れたりしやすくなるため、土嚢を置く、固定金具で固定する、といった対策が必要です。
- 漏えい管理:遮水壁を作るときは、周りの地面に水や材料が漏れ出さないよう、仮締切(仮囲い)や止水シートなどで工事エリアを囲む工夫がされます。特に継ぎ目やつなぎ目は漏れやすいので、ゴム製止水材やモルタルを詰めてすき間を埋めます。
3. 設計で重視する性能指標
- 透水係数(k値):材料や改良体の透水性を表す値で、値が小さいほど水を通しにくいです。遮水壁では非常に低い透水係数が求められ、一般的に1.0×10⁻⁸m/s以下が目安とされます。設計時の算定で浸透量や浸透流による圧力が決まり、これが安全性に直結します。
- 遮水深さ(有効長さ):地下水面や透水層を遮断するための深さを指します。浅すぎると地下水が壁の下を通り抜ける(横漏れ)ため、適切な深さ設定が必要です。一般的に「地下水が流れる透水層すべてをしっかり覆い、その下の不透水層に1m~2.5m程度しっかり根入れする」ことが基準とされています。
- 接合部・継手の性能:連続した壁であっても継手や接合が弱いとそこから水が漏れるため、接合方法やシーリング技術が重要です。
- 耐久性・耐食性:鋼矢板や金属部材は腐食対策が必要です。コンクリート系でもアルカリ骨材反応や劣化を考慮します。遮水壁は長期にわたり機能させる必要があり、劣化で性能が低下すると重大な問題になります。
4. 施工手順
- 地盤調査:ボーリングや地下水位測定、土質試験で地盤の性状を把握します。土質や地下水条件で最適な工法が変わり、透水係数や深さを決める基礎情報になります。
- 設計・配筋・仮設:施工に必要な設計図、仮締切や排水計画を立てます。
- 掘削・攪拌・注入:トレンチ掘削やミキサでの撹拌、ジェットグラウト注入などを行い、不透水体を形成します。ベントナイトスラリーで周囲土を支保しながら掘り進めることもあります。
- 継手処理・シール:隣接ブロック同士の継ぎ目をシールして連続性を確保します。
- 品質管理(試験):透水試験や採取供試体による圧縮強度試験、出来形確認を行います。設計どおりの透水性能や強度が確保されているかを確認するためです。
- 養生・仕上げ・点検:完了後の養生や長期の点検計画を立てます。
5. 施工上の課題と注意点
- 浮力対策:遮水体内に水が入った場合、浮力で構造物やパイプが浮き上がることがあります。浮上は配管の変形や機器のずれを引き起こし、機能障害につながります。対処法としては係留や重りを設置して物理的に持ち上がらないように働きかける方法や、段階打設として何回かに分けて注入することで、浮力が急激にかかるのを防ぎ、埋設物を安定させる方法があります。
- 施工時の漏えい管理:掘削時や注入時に周囲地盤へスラリーやセメントが流出すると、近隣の地下水や構造物に影響を及ぼす可能性があります。うまくコントロールされない注入は地下で新しい水の通り道を作ってしまうからです。そのため、観測井戸を設置した定期的な地下水の測定や、注入圧力・注入量をモニタリングするなど、厳格な管理と監視が必要となります。
- 周辺地盤への影響:掘削や注入による地盤応力の変化で沈下や亀裂が発生することがあります。設計段階で地盤解析を行い、必要であれば地盤改良や補強を行います。
- 化学的影響:地下水のpHや溶存塩類が材料(特にベントナイトやコンクリート)に与える影響を考慮する必要があります。これにより、化学的環境によって材料の遮水性能や強度が長期的に劣化することを防ぎます。
6. 維持管理・点検
遮水壁は設置して終わりではなく、定期点検と維持管理が重要です。点検項目には、目視による出来形確認、地下水位や浸透量のモニタリング、供試体の経年試験結果確認、腐食やひび割れの調査などがあります。万が一劣化や漏水が確認された場合は、局所的に補修・再注入(グラウト注入)や追加の遮水工を行います。継続的な点検を行うことで、初期にはわからなかった微少な経路が時間経過で拡大し、重大な漏水に発展する可能性を未然に防ぎます。
7. 環境配慮と法規
遮水壁は汚染土壌や地下水汚染拡散防止にも用いられます。埋立地や産廃処分場の周囲に遮水壁を設けることで、有害物質が地下水へ移動するのを抑えることができます。ただし遮水壁をつくることで地下水流路が変わり、別の場所で水位や水質の変化が起きる可能性があるため、環境影響評価や関係法規(地下水保全、廃棄物処理法など)に沿った設計が必要です。人為的に水理条件を変更することで生態系や既存の地下水利用に影響を与える可能性があるためです。
8. よくある疑問
- Q:遮水壁は永久に効くのか?
永久ではありません。材料の劣化、地盤の変動、継手部の損傷などで性能が低下することがあります。だからこそ定期点検と必要な補修(グラウトや追加の遮水工)が重要です。 - Q:鋼矢板と連続地中壁、どちらがいいか?
用途によります。鋼矢板は施工が速く仮設に向きますが、長期耐久性や継手からの漏水リスクがあるため恒久構造には補強や防食処理が必要です。連続地中壁は高い恒久遮水性が期待できますが施工コストが高くなりがちです。 - Q:遮水壁で地下水位はどう変わるか?
局所的には地下水位が上昇したり低下したりします。遮水壁は浸透経路を遮断するため、遮水体の上流で水位が高くなる一方、下流では低くなることがあります。これが周辺地盤や除水設備に与える影響を設計時に検討します。 - Q:グラウト注入はなぜ使うの?
既存の漏水経路や間隙がある場合、グラウト注入で隙間を充填して遮水性を回復させるためです。局所補修として最も使われる手段の一つです。
9. 学びを深める:教材・ツール
ここまでの内容を、資格学習や現場理解につなげたい方へ。
■ 書籍(基礎〜応用を自学)
■ 現場理解に役立つツール
まとめ:遮水壁は浸透流を遮断するための重要な構造物
遮水壁は、連続地中壁、トレンチカット、鋼矢板といった多様な工法があり、現場条件(地盤、地下水、施工スペース、経済性)に応じて選択されます。設計では透水係数や遮水深さ、継手の処理、耐久性を重視し、施工時には浮力対策や漏えい管理、周辺地盤への影響を慎重に扱う必要があります。さらに環境配慮と法規の順守、長期的な維持管理(点検・補修)が不可欠です。なぜ遮水壁が必要かという根本は、地盤が水を通す性質を持つためであり、それを人工的に遮断して安全性と環境保全を確保するためです。

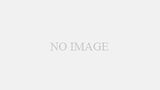
コメント