土木工事では、掘削作業や地下構造物の建設時に、周囲の地盤を安定させることが重要です。「土留(どどめ)」とは、土砂崩れを防ぎ、作業の安全を確保するための技術です。ここでは、土留の役割や主な工法、選定基準、設計のポイントについて説明します。
土留の基本的な役割とその仕組み
「土留」とは、その名の通り「土を留める」ための技術です。掘削した穴の側面や地下空間を一時的に支え、土砂が崩れるのを防ぎます。特に、深い掘削を伴う工事や、地下水が多い場所では、土留が不可欠です。また、周囲の地盤や建物への影響を最小限に抑える役割もあります。
土留が土を留めることができるのは、以下の仕組みによるものです。
- 壁の強さ
土留めの壁は、鉄やコンクリートなど、丈夫な材料を用いる事が一般的で、土の重みや押す力に負けない材料を用います。 - 摩擦の力
土と壁の間には物と物がくっつこうとする摩擦力が働きます。この摩擦力が、土が滑り落ちるのを防いでいます。これは例えば、本を机に押し付けながら動かそうとすると滑りにくくなるのと同じ原理です。 - 土の押し返す力
壁の前の土(掘った側)も、実は壁を押し返しています。この力も、後ろの土が押してくる力とバランスを取っています。 - アーチの形
土留めの周りの土は、アーチ型の力の流れを作ります。これによって、土の重みが分散されて、一箇所に集中しにくくなります。たとえば、石でできたアーチ橋が崩れないのは、この力の流れが橋全体を支えているからです。同じように、土留めでもこのアーチ作用が崩壊を防ぐ重要な役割を果たしています。 - 支える構造 必要に応じて、支保工と呼ばれる壁をつっぱり支える棒や梁を設置します。これらが壁を強く支えて、安定させます。
土留工法の主な種類と特徴
土留工法は、現場の地盤条件や施工環境に応じてさまざまな種類があります。以下に主要な工法を紹介します:
親杭横矢板工法
- H形鋼を親杭として地中に打ち込み、その間に木製や鋼製の板を横に渡して支えます。
- 比較的コストが安く、小規模工事の山留壁として使用されます。
- 浅い掘削現場に適しており、地下水が少ない場所で効果的です。
- 止水性が低いため、地下水が多い場所には不向きです。
鋼矢板工法
- 鋼製の板(シートパイル)を連続して地中に打ち込みます。
- 止水性が高く、幅広い掘削現場に対応できます。
- 軟弱な地盤や地下水位が高い場所でも使用可能です。
鋼管矢板工法
- 鋼管を地中に打ち込み、連結して壁を形成します。
- 高強度で耐久性が高いため、長持ちする壁を構築することができます。
- 軟弱な地盤や水中工事で高い効果を発揮します。
- 騒音や振動が少なく、環境に配慮した工法です。
地中連続壁工法
- 地中に連続的な壁を作り、セメントや鋼材で補強します。
- 耐久性が高く、トンネル工事などで使用されます。
- 施工時の振動や騒音が少なく、岩盤から軟弱地盤まであらゆる地盤で施工可能です。
- 止水性が高く、壁体の強度が高いのが特徴です。
土留工法の選定基準
工法を選ぶ際には、以下の条件を総合的に考慮する必要があります:
- 地盤条件
土質や地盤の強度(N値)、地下水位などを調査し、適切な工法を選びます。 例えば、軟弱地盤では高い支持力を持つ工法が必要です。 - 施工条件
掘削深さや使用する重機の可否、現場の広さなどが選定に影響します。特に都市部で工事をする場合、現場が狭いことが多く工法の選定には注意が必要です。 また、掘削深さが深い場合、大きな機械が必要となる場合がありますが、現場へ機械を搬入することができるか、事前に搬入経路を確認しておくことも大事です。 - 環境条件
周辺施設や地下埋設物への影響、騒音や振動対策も考慮します。 - 止水性能
地下水位が高い場合は、止水性能が高い工法が適用されます。土留での止水だけでは十分でない場合、周辺の地盤を改良するなど、地下水の影響を減らすための対策が必要となる場合があります。
土留設計のポイント
土留の設計には、土が壁を押す力(土圧)を正確に理解することが重要です。土圧は以下の要素で変化し、土留の安全な設計に直結します。
土圧を決める4つの要素
- 土の種類と性質
- 砂質土(さらさらした土):水を通しやすく、土圧は比較的小さいが崩れやすい。
- 粘土質土(ベタベタした土):水を通しにくい。濡れると重くなり、土圧が急増する。
- 地下水の影響
- 地下水があると、土が水を含んで重くなり、さらに「水圧」が加わります。そのため、地下水位が高い場合、土留め壁は「土+水」の両方の力に耐える設計が必要となります。
- 掘削の深さ
- 深く掘るほど、上からの土の重みが増し、土圧が大きくなります。
- 深さ3mを超えると「重要な土留め工事」として扱われ、大規模掘削として特別な安全基準が適用されます。深さが3m以上か以下かで、設計基準が変わると覚えて起きましょう。
- 地震の影響
- 地震時は「動的土圧」が発生し、一般的には通常時の1.5倍の力がかかると想定します。
設計の5大ポイント
- 安定性の確認
- 土留め壁が倒れたり、滑ったりしないかを計算します。
- 排水対策
- 地下水位が高い場合は、排水対策を適切に実施することで、水圧で壁が壊れてしまう可能性を低減させます。
- 安全係数
- 想定する土圧より1.5倍強い設計にすることで、予期せぬトラブルに対応します。
- 材料選び
- 土の種類に応じた材料を選択。 砂質土:水の侵入を防ぎながら軽量で施工しやすく安定した支持力を持つ鋼矢板 粘土質土:高い剛性と止水性能で柔らかい地盤でも安全に掘削できる地中連続壁 など
- モニタリング
- 工事中は壁の傾きやひび割れを計測し、異常がないか確認します。
- 異常が確認された場合は、状況の確認と原因の特定を行い、傾きが進行しないよう補強したり、壁が安定するまで工事を中断し、安全性を確保します。
(参考)1.5倍安全係数の法的根拠
(1)道路公団の設計要領
- 道路土工仮設構造物工指針(旧日本道路公団)で長期荷重1.5倍を安全係数と規定
- 地震時などの短期的な荷重に対しては、この1.5倍を基本に計算
(2)労働安全衛生規則
- 安衛則第384条で「地山の崩壊防止措置」を義務付け
- 実務では安全率1.5以上を目安に設計されることが多い
(3)建築基準法
- コンクリート構造の許容応力度計算で短期荷重=長期荷重×1.5と規定
- 地震などの突発的荷重を考慮した設計基準
(参考)なぜ1.5倍が必要か?
(1)不確定要素の補償
- 土質調査誤差(±20%)
- 施工精度のバラつき
- 経年劣化の考慮
(2)荷重の組み合わせ
- 通常荷重(土圧+水圧)
- 地震荷重(通常の1.5倍)
- 周辺交通による振動荷重
(3)実務上のトラブル事例
近接工事の影響
鋼矢板の腐食(年0.1mm減少)
地下水位の予期せぬ上昇
土留は、土木工事において欠かせない安全技術であり、工事現場の特性に応じた選定と適切な施工が成功の鍵です。地盤調査や環境条件をしっかりと考慮し、最適な工法を選ぶことで、効率的かつ安全に工事を進めることができます。土留技術を正しく理解することは、将来の工事計画においても重要な役割を果たすでしょう。

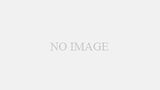
コメント