土木工事では、地面を掘る(掘削)作業を行うことがよくあります。しかし、掘ったままにしておくと、周りの土が崩れてしまいとても危険です。そこで登場するのが「土留(どどめ)」です。土留は、掘った場所の土が崩れないように支えるための壁のような構造物です。ここでは、土留の種類と各工法の特徴について説明します。
1.そもそも土留とは
土留は、掘削工事で土の崩れを防ぎ、作業の安全を守るための「支え」です。
土は本来、周囲の土や構造物によって押し合いバランスを保っています。深く掘ることでこのバランスが崩れ、周囲の地盤が動きやすくなり、建物や道路が傾いたり、作業員が危険にさらされたりします。特に水分の多い地盤ではこの影響が大きくなります。
そうならないよう、事前に土の側面に「壁」を作り、土の崩れを防ぎます。
2.土留の代表的な「種類」と「特徴」
ここでは、現場でよく使われる5つの代表的な土留の種類を紹介します。
① 矢板式土留
矢板式土留は、一般的には鋼(はがね)でできた「板(矢板)」を地面に何枚も並べて打ち込み、壁のようにして土や水が崩れたり流れ込んだりするのを防ぐ工法です。工事現場の周りに、しっかりした囲いを作るイメージです。
1.水を通しにくい(遮水性が高い)
鋼矢板は、一枚一枚がパズルのピースのようにしっかりかみ合う形になっています。板と板のすき間が小さいので、水が通りにくく、地下水や川の水が入ってくるのを防げます。必要に応じて「止水材」という水を吸ってふくらむ材料を使うことで、より遮水性能を高めることができます。
2.土や水の圧力に耐える
土や水は、掘った穴の壁に強い力(圧力)をかけます。矢板式土留は、鋼矢板などの強い板を地中に連続して打ち込むことで、壁全体が一体となり、外からの圧力を均等に分散して支える構造になっているため、その圧力をしっかり受け止めることができます。
3.いろいろな場所・状況で使える
水を通しにくく、土や水の圧力に強い壁を簡単に作れる矢板式土留は、川の近く、地下水が多い場所、地盤がやわらかい場所など、特に水や土が動きやすい現場で活躍します。また、洪水や水害のときに、仮設の堤防や護岸としても使われます。
4.工事が終わったあとも再利用できる
鋼矢板は丈夫な鉄でできており、打ち込んだり引き抜いたりしても壊れにくいため、工事が終わったら引き抜いて、また別の場所で使うことができます。これにより、資源を無駄にせず、環境にもやさしいです。
5.注意点
重機で強い力を加えて地面に押し込んだり引き抜いたりするため、騒音や振動が発生し、周辺の建物や住民に影響を与えることがあります。
また、矢板を引き抜くときに、矢板にくっついた土砂も一緒に持ち上げてしまい、地中に空洞ができてしまうことで、地盤が沈下したり、地面が動いたりすることがあります。特に、地盤がやわらかい場所や掘削が深い場合では、地盤の沈下や変動が大きくなりやすいので注意が必要です。
矢板の引抜きによる地盤の沈下や変動を防ぐには、「引抜同時充填工法」などで空洞をすぐに埋めることが効果的です。
また、矢板に摩擦を低減する材料を塗布し、矢板と土の摩擦を減らすことで、引抜き時に矢板に付いた土が一緒に持ち上がる現象を防ぐ方法もあります。
② 親杭横矢板工法
親杭横矢板工法は、まず「親杭(おやぐい)」と呼ばれる太い杭(主にH形鋼)を地面に一定の間隔で打ち込みます。そのあと、土を掘りながら親杭と親杭の間に「横矢板(よこやいた)」という板(多くは木製)を横向きに差し込んでいき、壁のようにして土が崩れるのを防ぐ方法です。
1.コストが安い・工事が簡単
親杭横矢板工法は、主にH形鋼の親杭と木製の横矢板を使用します。これらの材料は比較的安価で入手しやすく、工事手順もシンプルです。特別な機械や高度な技術が不要なため、作業が効率的に進み、小規模な工事や浅い掘削でコストを抑えられます。
2.遮水性(水を止める力)は低い
木製の横矢板は板同士の隙間ができやすい構造です。木材は鋼矢板のように密着した連続壁を形成できず、水が隙間から通り抜けやすいため、地下水が多い場所や水止めが必要な現場には不向きです。
3.高低差のある場所や固い地盤に向いている
親杭が地盤にしっかり固定されることで、段差のある敷地でも土の流出を防げます。固い地盤では親杭の固定力が高まり壁が安定しますが、軟弱地盤では親杭が固定されず壁が崩れやすくなるため適しません。
4.工事の進み具合に合わせて作業できる
親杭を先に打ち込み、掘削と同時に横矢板を差し込む段階的な施工が可能です。これにより、現場の状況や掘削の深さに応じて柔軟に作業を進められます。
5.設置方法のバリエーションが多い
親杭の間隔や横矢板の種類(木製・鋼製)を調整できる設計の自由度の高さが特徴です。地盤条件や掘削深さに応じて最適な設定を選べるため、多様な現場環境に対応しやすくなります。
③ 重力式擁壁
重力式擁壁は、コンクリートや石などの「重さ」を利用して、土が崩れるのを防ぐ壁です。壁自体がとても重く、その重さで土をしっかり押さえつけて支えます。
1.壁の重さで土を支える
重力式擁壁は、分厚くて重いコンクリートや石でできており、その「自重(じじゅう)」=自分自身の重さで土が壁を押す「土圧」に対抗します。壁が重いほど、土圧に負けずにしっかりと土を支えることができます。これは、壁自体が動かない「おもり」のような役割を果たしているからです。
2.シンプルな構造
重力式擁壁は、無筋コンクリートや石で作られます。分厚くて重い材料を積み上げるだけなので、構造が単純で施工がしやすく、昔から多くの場所で使われてきました。形が単純なため、設計や施工の手間が少なく済みます。
3.高さに限界がある
壁を高くするほど、土圧も大きくなるため、それに対抗するには壁をさらに重く・分厚く作る必要があります。しかし、壁が重くなりすぎると、地面(基礎地盤)がその重さを支えきれなくなり、地盤の沈下や壁が転倒する危険性が高まります。そのため、重力式擁壁は一般的に高さ5mくらいまでに使われることが多いです。
5mを超えるような高い重力式擁壁では、地震の揺れや風の力(風荷重)などの外力も無視できなくなり、これらを考慮した厳密な構造計算や設計が必要になります。実際、国や自治体の設計基準でも「高さ5mを超える擁壁は、原則として地震時の検討を行う」と定められており、より高い安全性が求められます。
このような理由から、安定して安全に使える高さの目安として、重力式擁壁はおおむね5m以下で使われることが一般的です。
4.水抜き穴が必要
壁の後ろに雨水や地下水がたまると、土圧がさらに強くなって壁を押し倒そうとします。水は土よりも動きやすく、壁の安全性を大きく下げてしまうため、壁の下の方に「水抜き穴」を設けて、たまった水を外に逃がすことで、壁にかかる力を減らし、壊れにくくしています。
水抜き穴の設置は、宅地造成等規制法施行令や各種設計基準で、「壁面の面積3平方メートル以内ごとに少なくとも1個」と義務付けられています。
5.地盤が安定している場所に向いている
重力式擁壁はとても重いので、地盤がしっかりしていないと壁が沈んだり傾いたりしてしまいます。逆に、地盤が固く安定していれば、壁の重さをしっかり受け止めてくれるので、長期間安全に使うことができます。
④ アンカー式土留
アンカー式土留は、掘った土の壁(たとえばコンクリートや鋼板の壁)が倒れたり動いたりしないように、「アンカー」と呼ばれる強いワイヤーや棒を壁から地面の奥深くまで斜めや水平に打ち込み、その引っ張る力で壁を固定する方法です。
1.深い掘削や高い壁に強い
アンカーを使うことで、壁だけで土圧を受け止めるよりも、はるかに安定して支えることができます。アンカーが壁を後ろから引っ張ることで、深い穴を掘る場合や高い土留め壁が必要な場所でも、壁が倒れたり動いたりしにくくなります。
2.土地を有効に使える
アンカーで壁をしっかり固定できるため、壁自体を分厚くする必要がなくなります。つまり、壁を薄く作れるので、敷地を広く使うことができ、都市部など土地が限られている場所でも有効です。
3.アンカーの仕組み
アンカーは「引張材(ひっぱりざい)」と呼ばれる強いワイヤーや棒でできており、これを地中の固い地層にしっかり固定します。壁とアンカーの間には「受圧板」という板を使い、アンカーが受ける力を壁全体に均等に伝えます。これにより、壁の一部にだけ力が集中せず、全体で土圧を受け止められます。
4.施工には注意が必要
アンカーを打ち込むには、周囲に十分なスペースと、地中にしっかりと固定できる強い地層が必要です。もし地盤が弱かったり、アンカーが短すぎたり細すぎたりすると、十分な引っ張る力が出ず、壁が安定しなくなります。そのため、アンカーの長さや太さ、引っ張る力などを現場ごとにしっかり設計しないと、安全で効果的な土留めができません。
⑤ 補強土壁
補強土壁は、土の中に「補強材(ほきょうざい)」と呼ばれる鉄の帯や合成樹脂などの強い材料を何層にも入れながら、土を積み上げていく壁の工法です。壁の表面にはコンクリートやブロックなどを使って、見た目もきれいに仕上げます。
1.土と補強材が一体になることで強くなる
土の中に補強材(強いシートや金属の帯)を入れると、土と補強材が摩擦でくっつき、「引張力(ひっぱりりょく)」を発揮します。土が動こうとすると補強材が引っ張られ、綱引きのように抵抗するため、土圧を分散させます。これにより、土だけの斜面より10倍以上の安定性が得られ、急勾配や高さ20m級の壁でも崩れにくくなります。
2.高い壁や垂直に近い壁も作れる
層状に配置した補強材が土を一体化させるため、壁全体がグラグラせず、しっかりした形を保ちます。設計上は垂直(90度)に近い角度でも安定し、壁の安定性を保つために、壁面を垂直ではなく後ろに傾けて設計する従来の擁壁より30~50%省スペース化できます。土地を効率的に活用できるため、道路や建物の敷地を広く確保することができます。
3.地震や地盤沈下にも強い
補強土壁は「フレキシブル構造」といって、多少の地盤沈下や地震の揺れにも柔軟に対応できます。壁全体が一体化しているので、部分的に壊れにくいのが特徴です。
補強土壁は「フレキシブル構造」といって、補強材がひび割れの発生を抑え、力を分散させるため、多少の地盤沈下や地震の揺れにも柔軟に対応できます。実験では、震度6強の揺れでも崩壊しないことが実証されており、剛性構造の擁壁(コンクリートなどの硬い材料だけで作られ、形がほとんど変わらない壁)より耐震性が高い特性があります。
4.特殊な機械や熟練工がいらない
補強土壁に使う材料は、あらかじめ決まった形や大きさで作られているので、組み立てが簡単で、特別な機械や高度な技術がなくても工事ができます。これにより、施工コストを20~30%削減できます。
3.土留工法の選び方と設計のポイント
■ 土留工法の選び方
先に述べた各工法の特徴を踏まえ、一般的には次のような条件に合わせて選びます。
① 地下水が多い・水を通したくない → 矢板式土留
水を通しにくく、しっかりと土や水の圧力を受け止めることができます。地下水が多い場所や川の近くの工事、仮設の堤防などにも向いています。
② 小規模で浅い工事、コストを抑えたい → 親杭横矢板工法
材料が安く、工事も簡単なため、小さな工事や浅い掘削に向いています。ただし、水を止める力は弱く、地下水の多い場所には不向きです。
③ 壁の重さで支えたい、構造をシンプルにしたい → 重力式擁壁
シンプルで施工しやすいのが特長です。ただし、高くなると重さが増し、地盤が沈むリスクがあるため、一般的に高さ5m以下で使います。
④ 深く掘る・土地を有効に使いたい → アンカー式土留
深い掘削や高い壁でも安定し、壁を薄く作れるので敷地を広く使えます。ただし、アンカーを打ち込むスペースや地盤の強さが必要です。
⑤ 高い壁・地震に強い・省スペースにしたい → 補強土壁
地震や地盤沈下にも強く、垂直に近い角度の高い壁でも作れます。施工も簡単で、コストを抑えられるのが利点です。
■ 設計のポイント
設計では、次のような点に注意して、安全で効率的な土留工法を決めます。
① 地盤の硬さ
固い地盤ではどの工法も安定しますが、やわらかい地盤では注意が必要です。特に親杭横矢板や重力式擁壁のような「地盤の強さに頼る工法」は、地面が重さや力をしっかり支えられないため不向きです。そのため、やわらかい地盤では、地盤改良や他の工法(補強土壁やアンカー式土留など)を検討する必要があります。
② 水の量
水が多い現場では、遮水性のある矢板式土留が効果的です。水抜き穴の設置や止水材の使用も重要です。
③ 掘削の深さ・高さ
掘る深さや作る壁の高さによって、選べる工法が変わります。深く掘る場合はアンカー式、浅い場合は親杭横矢板などが適しています。
④ 施工スペース・周囲の環境
都市部などでスペースが限られている場合は、省スペースでできる補強土壁やアンカー式土留が向いています。
⑤ 振動・騒音の影響
周辺への影響が大きい場合は、騒音・振動が少ない工法を選ぶことが求められます。矢板式は騒音や地盤への影響があるため注意が必要です。
土留は、土木工事において「見えないけれど重要な存在」です。掘削の深さや地盤の種類、水の有無など、さまざまな要素を考慮して最適な土留の種類を選ぶことが、安全で効率的な工事につながります。
今回紹介した矢板式土留、親杭横矢板工法、重力式擁壁、アンカー式、補強土壁など、それぞれに得意な現場や条件があります。土留の働きや違いを知っておくことで、将来、土木の仕事に関わるときにきっと役立つはずです。

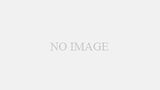
コメント