土木工事では、地下を掘ったりトンネルをつくったりする場面がよくあります。そのときに重要になるのが「支保工(しほこう)」です。支保工は、掘った穴の周りが崩れないようにするための“骨組み”のようなもので、安全な工事を進めるために欠かせない存在です。
ここでは、支保工の役割や種類、安全性の確保の方法などを説明します。
支保工とは
支保工とは、掘削した土の崩壊を防ぐために設置する仮設の構造物です。
たとえば、トンネルを掘ったときや、地下構造物(地下鉄、下水管など)をつくるとき、周りの地盤が崩れてくるおそれがあります。そこで支保工を設置し、土圧(どあつ)や岩盤の重さに耐えるように支えるのです。
地盤は、掘削前は周囲の土が支え合って安定していますが、いったん掘るとバランスが崩れ、土砂崩れのような状態になることから、水分や振動の影響で簡単に崩れることがあります。これを防ぐのが支保工の役割です。
支保工の主な役割
1.地盤の崩壊防止
支保工は、掘削した空間の周囲の地盤が崩れてくるのを防ぐために設置されます。支保工は、こうした土圧や岩圧に耐えて、地盤が崩れ落ちてくるのを防ぐ役割を果たします。
2.作業員の安全確保
支保工は、工事現場で作業する人たちの安全を守るためにも不可欠です。地盤が崩れたり、岩や土砂が落ちてきたりすると、作業員が大きな危険にさらされます。支保工を設置することで、現場内での事故やケガを防ぎ、安全な作業環境を確保できます。
3.周辺構造物(建物や道路など)への影響を防ぐ
支保工は、工事現場だけでなく、周囲にある建物や道路などの構造物が地盤の変動や崩壊の影響を受けないようにする役割も持っています。支保工が地盤を支えることで、周辺の構造物が沈下したり、傾いたり、損傷したりするのを防ぎます。
4.施工空間を確保する
支保工は、掘削した空間が崩れて狭くなったり、作業スペースが失われたりしないように、必要な広さの施工空間を保つ役割もあります。これにより、工事が計画通りに進められ、作業効率も向上します。
5.地下水の流入をコントロールする
地下水が掘削空間に流れ込むと、地盤が不安定になったり、作業が困難になったりします。支保工は、地下水の流入を抑えたり、コントロールしたりするための設備と組み合わせて使われることが多く、地盤や構造物の安定性を保つうえで重要な役割を担っています。
支保工の使われる場面
支保工は、次のような土木工事で使われます。
- トンネル工事
- 山岳トンネルでは、山の中の岩盤や土を掘り進める際、掘削した空間の天井や側面が崩れないように、鋼製のアーチや吹付けコンクリート、ロックボルトなどの支保工を設置します。地盤が弱い場所や亀裂が多い岩盤では、特に支保工が重要です。
- 都市部のシールド工法でも、浅い地層や、地盤が非常に軟弱な場合などで、トンネルを掘る際に周囲の地盤を一時的に支えるため、シールドマシンの直後で支保工が使われることがあります。
- 立坑や斜坑の掘削
- 立坑は、地下深くまで垂直に掘る大きな穴で、下水道や共同溝、電線の設置などで使われます。掘削中、穴の側面が崩れてこないように、鋼製やコンクリート製の支保工を段階的に設置していきます。
- 斜坑も同様に、斜めに掘る場合でも周囲の地盤を支えるために支保工が必要です。
- 山留め工事
- 建物の基礎工事や地下室、地下鉄の駅など、地面を深く掘るときに土留壁(矢板や鋼板など)を設置し、さらにその壁が倒れたり外側に動いたりしないように、内側に「切梁」や「腹起こし」などの支保工を組みます。これにより、掘削中の安全と周囲の地盤の安定を確保します。
- 山の斜面や法面が急で、崩れやすい場所では、鉄筋やアンカーなどの補強材を地面に挿入し、吹付けコンクリートや金網と組み合わせて支保工として使うことで、斜面全体の安定を図ります。これは道路や構造物の建設時だけでなく、災害対策としても用いられます。
支保工の種類
支保工にはいくつかの種類があり、工事の内容や地盤の状態に応じて使い分けられます。どの支保工も、「掘った空間が崩れないように支える」という共通の目的がありますが、使う場所や作り方によって種類が分かれています。
- 山留め支保工 山留め支保工は地面を掘るときの土止め全体を指し、その中で「鋼製支保工」や「木製支保工」を現場の規模や条件に応じて使い分けます。
- 鋼製支保工 鋼材でできており強度があります。大きな力がかかる大規模な掘削で用いられ、長さや形を調整しやすく、繰り返し使うこともできます。
- 木製支保工 鋼製よりも軽くて扱いやすく安価ですが、強度が弱いので大きな力がかかる大規模な掘削ではあまり使われません。小さな工事や、短い期間だけ必要なときに使われます。
- セントル(型枠支保工) トンネルの内側をアーチ型に仕上げるときに使う、型枠を支えるための枠組みです。 その型枠の中にコンクリートを流し込むことで、アーチ状の内壁(覆工コンクリート)がきれいな形で固まります。
- ライニング支保工 ライニング支保工は、トンネルの内側をコンクリートなどで仕上げる際に、セントル(型枠支保工)を用いて型枠を支え、形状を保つための一時的な支えです。 コンクリートが固まってトンネルの内壁(ライニング)が完成した後、セントルを含むライニング支保工は取り外されます。
支保工に使われる材料
支保工には、以下のような材料が使われます。使う材料は、工事の規模や地盤の状態、施工方法によって決まります。
- 鋼材(H形鋼、鋼管、鋼矢板)
強くて繰り返し使えるため、大規模なトンネル工事や深い掘削に使われます。鋼材は、重い土圧や岩盤の重さにも耐えられるのが特徴です。
- 木材
軽くて加工がしやすく、小規模な工事や狭い場所での仮設支保工に使われます。ただし、耐久性が低く、水に弱いという弱点があります。
- コンクリート型枠
トンネルなどで使われる型枠は、支保工の役割も果たします。施工後、そのままライニング(トンネルの内壁)と一体化させることもあり、工期短縮につながります。
支保工の施工手順
支保工の設置は、工事の安全を確保し、効率よく作業を進めるため次のような手順で行います。施工や管理には多くのポイントがありますが、すべては「安全に工事を進めるため」「作業員の命を守るため」という共通の目的に基づいています。
1.地盤調査・設計
支保工を設置する前に、地盤の性質を調べます。たとえば、地盤が硬いのか柔らかいのか、地下水が多いのか少ないのかなどを調査します。こうした情報をもとに、支保工の種類や構造を設計します。これは、地盤によって崩れやすさや必要な支え方が大きく変わるためです。
2.掘削と同時に支保工設置
支保工は、掘削と同時に設置するのが基本です。これを「先行支保」と呼びます。掘りすぎてしまうと、地盤が崩れたり、地下水が流れ込んだりする危険があるため、少し掘っては支保工を入れるという作業を繰り返します。
3.固定・補強
設置した支保工は、そのままだと地盤の圧力や振動で動いてしまうため、しっかりと固定し、必要に応じて補強します。特にトンネルなどでは、上からの荷重が大きいため、補強が欠かせません。
4.撤去・永久構造物への切り替え
工事が終わったあとは、支保工を取り除くか、恒久的な構造物に置き換えます。たとえばトンネル工事では、支保工の代わりに「ライニング」と呼ばれるコンクリートの内壁をつくり、トンネルを完成させます。これは、仮設で支えていた構造を、長期間使える強固な構造にするためです。
支保工の安全対策と設計基準
支保工は一時的な仮設構造物ですが、現場で働く人々の命を守る重要な役割を持ちます。そのため、次のような安全対策や設計基準を守る必要があります。
- 設計時に土圧や地下水圧を計算する
支保工には、周りの土や岩、地下水の圧力がかかります。これらの力を正確に計算しないと、支保工が崩れたり変形したりする危険があります。安全を確保するために、計算は非常に重要です。
- 地盤調査に基づいた設計基準(道路土工指針など)を守る
国や自治体には、支保工を設計するための基準や指針があります。たとえば「道路土工指針」などが代表例です。これらの基準を守ることで、どの現場でも一定の安全性が確保されます。
- 支保工の沈下や傾きを常に監視する
設置後も、支保工が沈んだり傾いたりしていないかを測定器や目視で確認します。地盤の変化は急に起きることもあるので、常に監視することが大事です。
- 定期的な点検・補修を行う
支保工は工事期間中ずっと安全に使わなければなりません。そのため、定期的に点検して、傷みやゆるみがあればすぐに補修します。こうした点検を怠ると、小さな異常が大きな事故につながる危険があります。
支保工は、土木工事において「掘る」作業に欠かせない安全対策の一つです。掘削中の土や岩が崩れないように支えることで、作業員の命を守り、周囲の建物やインフラに影響を与えないようにします。種類もさまざまで、工事の内容や地盤の状態に応じて最適な支保工が設計されます。
安全で確実な工事を実現するためには、支保工の適切な設計と施工、そして常に安全を意識した管理が重要です。

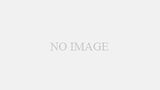
コメント